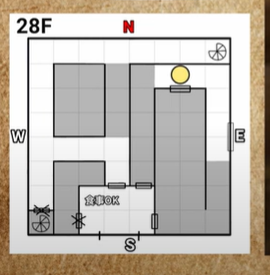アフリカ系女性で初めてノーベル文学賞を受賞したト二・モリスンが、実際の事件を基に奴隷制度の傷痕について描いた話。
奴隷としての過去を持ち、現在は自由の身になったセサは、娘のデンヴァーと二人で暮らしている。
母娘は平穏に暮らしていたが、家で起こる怪奇現象に悩まされていた。
そこにかつて、セサが奴隷として過ごしていたスイートホームで同じ奴隷の立場だった、ポールDがやって来る。
ポールDは屋敷から幽霊を追い払い、セサと愛し合うようになったが……。
序盤、セサの過去やなぜ幽霊に悩まされるようになったのか、なぜ幽霊に悩まされながらもセサたちは家から離れようとしないのかはわからない。
ポールDが登場した時、ポールDとセサがいたスイートホームの主人はとても寛容であり、二人は一般的な奴隷のように虐待もされず、仕事も任されて人として尊重されていたという思い出が語られる。
ところが話が進むにつれて、セサもポールDも忘れていた過去を、不意に思い出すようになる。
セサやポールDは奴隷という身分から脱け出し、今は穏やかに暮らしているように見える。
だがそれは、過去の記憶を封印することによって、どうにか保たれている平穏だった。
セサやポールDたちは、スイートホームにいた当初、寛容な主人(白人)によって、人としての自我を与えられた。他人から尊重されること、信頼されることを通して、自らの内部に「人間」を形成していった。(作内では「ポールDたちは、一人前の男として扱われた」という言い方がされている)
ところが主人(白人)が変わっただけで、彼らの内部に形成された「人間」はズタズタに切り裂かれる。
セサの新しい主人となった「先生」は、甥たちにセサの人間的な特徴と動物的な特徴をそれぞれ分けて記入するように命ずる。
ポールDは暴れないように馬用のハミをくわえさせられ、四十数人まとめて鎖につながれて強制労働に狩りだされ、声を出すことも禁じられる。
女性はもちろん、男であっても脅され面白半分に性的な行為を強いられる。
セサやエラ、ベビー・サッグスといった女性たちは、日常的に性的虐待を受け、父親が異なる子供を次々と産む。そしてその子供たちがまた主人の資産となる。
セサたちの過去の記憶は、どれかひとつを取っても惨く、「人としての尊厳を砕かれた」と表現するしかない。
セサの義母ベビー・サッグスが言ったように、主人が寛容であるか残酷であるかは根本的には関係がない。
彼らの自我や存在は白人によって作られ、そして破壊される。
息子のハーレに買い取られ、自由を手に入れたベビー・サッグスはその時初めて「自分」を発見する。
ほんとうの「自分自身」になったことのない自身が見捨てられ、荒れはてた彼女の中心に居座っていたのだ。(略)
自分という人間を発見するための地図など、一度も手にしたことがなかったからだ。(略)
突然自分の両手が目に入り、目が眩み、簡単至極で同時にきらきらと輝くような「この手はわたしが持っている。この二本の手はわたしの手」という思いが生まれた。
何かがドキンドキンと音を立てているのを感じ、他にも新発見をした。
自分の心臓の鼓動だった。
いままでずっと胸の中で鳴っていたのか? このドキンドキンと打つものは?(略)
「何がおかしいんだ、ジェニー」(略)
「わたしの心臓がこどうしているんです」
その通りだった。
(引用元:「ビラヴド」トニ・モリスン/吉田廸子訳 早川書房 P287‐P290/太字は引用者)
ベビー・サッグスは、自由になることで初めて「私」という概念を知り、「自分は自分である」と実感する。
このシーン自体はいいシーンだが、その背後にあるものを考えると寒々とした気持ちになる。
奴隷だったベビー・サッグスは「私」を与えられず、知ることもできなかった。
「私の手」は私のものではなく、私の心臓は私のものではない。自分の体内で心臓が脈打っていることすら実感することが出来ずにいたのだ。
自分を「わたし」と結びつける自尊心を、彼女たちはひとかけらも与えられずに生きてきた。
セサたちは自分たちがかつて「『わたし』を持たない家畜として扱われていた→人としての尊厳を奪われていた時の恐ろしい記憶」を心の奥底に固く閉じ込めて生きている。
その記憶を思い出してしまえば、「わたし」でいることが出来ないからだ。
だがそれでも、かつて奴隷だった時の記憶が次々と噴出してくる。
この記憶の浮かび上がりかたは、時系列順にもなっておらず脈絡もない。
つながりがあるものを見ることで、印象的なシーンが浮かび上がってきて、そこにまつわる思い出が紐を引っ張られたかのようにスルスルと表に出てくる。
その過酷で恐ろしい記憶が断片的に現れることで、彼らの過去にどんなことがあったが、なぜそれを無理矢理にでも忘れ去らなければ人として生きていくことが出来ないのか。読み手も追体験する。
セサはかつて、デンヴァーの姉である自分の娘を殺している。
デンヴァーの兄である、セサの二人の息子は、母親の子殺しを知って家を出て消息を絶った。
怪奇現象は、セサが殺した娘ビラヴドが起こしていたものだった。セサとデンヴァーはそう信じている。
セサがビラヴドを殺したのは、かつての自分のような目に合わせないため、娘の人間性を白人によって破壊されないためだった。
セサは自分の下に戻ってきたビラヴドにそう説明する。だがビラヴドの怒りは収まらず、二人は共に荒廃していく。
なぜ制度が社会的には解消されても、人の心を捕らえたままでいるのか。
「ビラヴド」を読むと、その制度が人の心にどんなものをもたらすのか、制度自体を表面上なくしたとしても、それに関わった人たちの内部をどれほど破壊し、変質させてしまうかが伝わってくる。
白人種は、外見はどうあろうと、黒人であれば、その皮膚の下にはかならずジャングルが潜んでいると信じていた。(略)
自分たち黒人は、どんなにやさしく、どんなに賢く愛情に満ちていて、どんなに人間らしいかを、白人に納得させようと力を尽くせば尽くすほど、黒人が、黒人自身にとっては異論の余地のない事実を白人に信じさせようとして、身をすり減らせば減らすほど、黒人の心のジャングルはますます深くなり、ますますもつれてくるのだった。
だがそれは(略)白い肌をした人々が黒人の心の中に種を蒔いたジャングルだった。
そして、ジャングルは育った。広がった。(略)
ついにジャングルは、種を蒔いた白人たちの心に侵入した。
一人残らずすべての白人に感染した。彼らを変えて別人にした。
血で汚し、分別を失わせ、さすがの彼らでも望んでいなかったような非道な行為に走らせたので、自分たちが種を蒔いたジャングルに恐れおののいた。
奇声を上げる狒々は自身の白い皮膚の下に住んでいた。
(引用元:「ビラヴド」トニ・モリスン/吉田廸子訳 早川書房 P402 /太字は引用者)
ジャングルの例えは、社会と個人の関係、制度と個人の内面がどう結びついているかを的確に表している。
セサもポールDもベビー・サッグスも奴隷という身分から脱け出し、今は自由の身で生きている。
だがかつて経験した出来事が、せざるえなかったことが、自分を形成するものとなり自分自身を苦しめる。
自分が味わったことを味合わせたくないと思い殺した娘に呪われ、子殺しの母として糾弾され続ける。
構造(システム)は、個人を形成する要素であると同時に個人がその一部となって形成するものだ。
その制度がもたらすものが自身の内部に「ジャングル」として生い茂り、他の人間の内部のジャングルと組み合わさって繁茂していく。そうすることで自身の内部のジャングルはますます深く暗くなっていき、その深さ暗さによって自分自身が変質していく。
だから脱け出すことが難しい。
直前に読んだせいか、「ビラヴド」はフォークナーの「八月の光」の批判のように読めた。
歴史と因習、差別や偏見がうずまく南部の街から出て行く(出ていける)存在として、「八月の光」は未婚の母・リーナを設定した。
それに対して「ビラヴド」では、子殺しをした母であるセサを主人公に据えている。
セサは自分が殺した娘に復讐されながら、自分がお前を殺したのは愛情からだ、お前は「ビラヴド(愛されし者)」だった、その墓碑銘を掘るために、自分は屠殺場で身を売りさえしたのだと叫ぶ。
「ビラヴド」の中では、セサと同じようにかつて黒人奴隷だったエラも、白人に犯されて産まれた自分の子供に母乳をやる気なんて到底起きず、放置したら死んだという経験を語っている。
「母性神話」に対する反発、批判的な意識を感じる。
被差別者側の視点によって、差別の歴史の悲惨さ、残酷さを描く話。
女性(母親)特有の痛みと葛藤を描くフェミニズム文学。
時系列や因果によってではなく登場人物たちの意識に沿って内容が描写されるモダニズム文学。(このあたりの語りの手法が「八月の光」に似ている)
近代に発明された「自我=わたし」とは何かを追及した実存的な文学。
「ビラヴド」は色々な読み方ができる。
何より読み物としてもとても面白い小説だった。
「八月の光」も大好きだけどね。
続き。